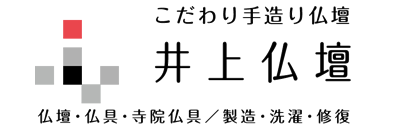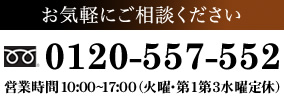約100年前の彦根仏壇のお洗濯、仏像の修復等。2尺8寸本三方開き、真宗大谷派
ホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。
日本を代表する産地彦根で、こだわりの手造り仏壇を製造しております、井上仏壇の井上昌一と申します。
彦根市のお客様より、約100年前の彦根仏壇のお洗濯、仏像の修復等をご依頼いただきましたので、作業の様子をご紹介いたします。
 彦根仏壇2尺8寸本三方開き 真宗大谷派 お洗濯(おすすめコース)・仏像修復等
彦根仏壇2尺8寸本三方開き 真宗大谷派 お洗濯(おすすめコース)・仏像修復等
今回は、代々長くお付き合いをさせていただいている手次寺(てつぎでら)のご住職様からのご依頼で、お仏壇のお洗濯(おすすめコース)をお任せいただきました。ご相談のお仏壇は本堂ではなく、ご住職様ご家族が住まわれていれる「庫裏(くり)」に安置されているものでした。先代のご住職であるお父様の三回忌を控えられ、「三回忌を迎えるにあたり、お仏壇を修理してきれいにしたい」とのご相談をいただきました。
お引き取り時・解体前
 こちらが今回お預かりしたお仏壇です。約100年にわたって大切に守ってこられた彦根仏壇です。
こちらが今回お預かりしたお仏壇です。約100年にわたって大切に守ってこられた彦根仏壇です。
彦根仏壇の高級品に証として押されている「焼印」がしっかりと残っていました。お洗濯のほか、お買い替えの選択肢もありましたが、守ってきたものをできれば残したいというご意向からお洗濯の方向でお話が進み、ご本尊の仏像とお仏壇は修理をすることになりました。
※お仏壇の洗濯や洗浄については、詳しくはこちらをご参考ください >>「洗濯・洗浄」
 お仏壇をお引き取りして、工房へ持ち帰ったところです。お洗濯の作業に入る前に、必ず現状のお写真を撮っておきます。
お仏壇をお引き取りして、工房へ持ち帰ったところです。お洗濯の作業に入る前に、必ず現状のお写真を撮っておきます。

色々な角度から記録写真を撮影します。金具、彫刻、蒔絵の向きや位置などを確認しつつ、多めにお写真を撮っています。こちらは、「三方開き」の扉をすべて開けた状態です。
 側面の扉を閉めて、お障子を閉めた状態です。金具の状態等もあわせて確認します。
側面の扉を閉めて、お障子を閉めた状態です。金具の状態等もあわせて確認します。

よく見ると金具に青錆(左)があり、ネズミがかじった跡(右下)も見られました。細かいところまで確認して写真に収め、解体作業に移ります。
解体・洗浄

記録を終えたら、いよいよ解体作業に入ります。釘を使って留められている箇所がお仏壇によって違うこともありますので、どこがどう留まっているのか、構造を確認しながら解体していきます。彫刻などを落とすと破損してしまいますので、傷つけないよう慎重に進めます。古いお仏壇では、サビついていたり、汚れが付いていたり、判別が難しい場合もありますので、職人の経験が活かされる作業です。

解体作業が進んでいます。手前では解体を進めながら、奥では洗浄作業も行っています。

洗浄の様子です。すべての部品をひとつひとつ丁寧に洗浄し、長年の埃や煤を洗い流します。洗浄作業は、よく晴れた天気の良い日に行います。水洗いした後は、太陽の光でしっかり乾燥させます。
木地直し

洗浄と乾燥が終わると、「木地直し」という工程に入ります。確認のために仮組をして、木地の傷んだ箇所を交換したり、歪みを直したりする工程です。今回は、ネズミ喰いのため台輪引き出しツカを交換(右下)、塩分を含んでいた中段下横桟(左)の交換等を行いました。錆が出ている箇所は木材が塩分を含んでいるため、交換する必要があります。

こちらはお仏壇の裏底です。移動のための「壇車」と呼ばれる木製の車輪が4つついていましたが、経年劣化でボロボロになっていました。このままではお仏壇の水平が保てず、歪みの原因になります。そこで、全ての車輪を木地職人さんがこのお仏壇に合わせて作り直して交換しました。白木の箇所が今回交換した箇所です。

お仏壇の内部です。上段の天板は、反りのため交換しています。印のある上段ツカは、塩分のため交換しました。引き出しは、割れのため蒔絵板を交換しています。そのほかにも細かくチェックして、必要な箇所の交換を行いました。木地直しでは、反りや割れがないか、水平を保てているかなどのほか、このあと塗りの工程に入るとその分厚みが増すので、引き出しの開閉がきつくないか、ゆとりが十分にあるかなど、細部にわたって確認します。特に昔のお仏壇はゆとりが少なくきつめになっているので、木地直しでの調整が重要です。解体して初めて見えてくる部分も多く、ご予算とのバランスを考えつつ、これからも長く受け継いでいただけるよう、専門家として最良のご提案をさせていただきたいと考えております。
塗り上がり

木地直しを終えたお仏壇は漆塗り職人さんのもとで塗りの工程に入り、約4ヶ月という長い時間をかけて塗りの工程が完了しました。
 艶やかな美しい仕上がりです。下地を丁寧に整えて何度も塗り重ねていくことで、表面が平滑になり深みのある艶が出て、新品と見紛うほどの美しい仕上がりになります。「お洗濯だから」と工程を省くことは一切せず、新しいお仏壇を作るのと全く同じ手間と時間をかけて塗り上げます。
艶やかな美しい仕上がりです。下地を丁寧に整えて何度も塗り重ねていくことで、表面が平滑になり深みのある艶が出て、新品と見紛うほどの美しい仕上がりになります。「お洗濯だから」と工程を省くことは一切せず、新しいお仏壇を作るのと全く同じ手間と時間をかけて塗り上げます。

塗りが終わったら、一度工房で仮組みをします。次に進む「金箔押し」の工程で、どの部分に金箔を施すかを正確に確認するためです。仮組みで最終確認を終えたら、再び解体して金箔押し職人さんのもとへと渡っていきます。
組み立て
 いよいよ最終の組み立てです。金箔が押され、艶消し金めっきをしてきれいになった金具を釘で取り付けていきます。
いよいよ最終の組み立てです。金箔が押され、艶消し金めっきをしてきれいになった金具を釘で取り付けていきます。
 まだ障子や扉はついていませんが、完成はもう間近です。最終確認をしながら、ひとつひとつ丁寧に組み上げていきます。
まだ障子や扉はついていませんが、完成はもう間近です。最終確認をしながら、ひとつひとつ丁寧に組み上げていきます。
仏像(仏身)修復
今回はお仏壇本体のお洗濯とは別に、ご本尊である仏像の修復も進めていました。
修復前

【本尊】仏像 5.0 仏身は修復 台座・光背は新調
こちらも100年以上前のものと思われる歴史のあるものです。私がお伺いした際には、かなり前に傾いて倒れそうで、非常に危ない状態でした。そのため、お仏壇より一足先にお預かりして修復に取り掛かりました。
修復のようす

今回台座と光背は新調いただくことになり、仏身のみを修復します。仏像の修復は、専門の仏師が行います。まず、剥離しかけている古い塗装を丁寧に取り除き、木地の状態に戻します。
 取り外しできる箇所は取り外して、欠けていた指を補修するなど木地の傷みを修復したあと、下地を施して彩色をしていきます。最後に、「古色仕上げ」をして仕上げています。
取り外しできる箇所は取り外して、欠けていた指を補修するなど木地の傷みを修復したあと、下地を施して彩色をしていきます。最後に、「古色仕上げ」をして仕上げています。
 ただ新品のようにピカピカにするのではなく、あえて艶を抑えて陰影等をつけることで、長年お参りされてきた雰囲気に仕上げています。お顔の表情も穏やかに美しく蘇りました。
ただ新品のようにピカピカにするのではなく、あえて艶を抑えて陰影等をつけることで、長年お参りされてきた雰囲気に仕上げています。お顔の表情も穏やかに美しく蘇りました。
※お仏像・お仏画の修復については、詳しくはこちらをご参考ください >>仏像・仏画の修理修復
納品
 彦根仏壇2尺8寸 本三方開き 真宗大谷派
彦根仏壇2尺8寸 本三方開き 真宗大谷派
いよいよご納品の日を迎えました。彦根仏壇2尺8寸、本三方開きのお仏壇です。「2尺8寸」は、屋根の横幅が2尺8寸、約85cmということを指しています。「本三方開き」は、正面と両側面が開く通常の三方開きよりもさらに本格的な格式の高い造りです。

【本尊】仏像 5.0 仏身は修復 台座・光背は新調
【両脇】仏画掛軸 そのまま 100代
お仏壇の内部です。仏像は白毫(びゃくごう(額の中央の突起))から脚の先までが約5寸(約15cm)、仏身は修復し、台座と光背は新調いただきました。両脇の掛け軸は、ご住職様のご希望で、あえて修理はせず、代々受け継いでこられた歴史をそのまま残しています。灯籠や輪灯は新調されて、輪灯瓔珞(ようらく)は洗浄や消しめっき加工を施して、輝きを取り戻しました。もちろん、すべて針金を外して、めっき後ひとつひとつつなぎ直ししています。

前卓などの木製の仏具も、お仏壇本体と一緒にお洗濯をさせていただきました。全て100年前から大切に使われているものですが、新品のような仕上がりです。

無事に先代ご住職様の三回忌までにご納品することができました。ご住職様やご親戚のお寺様からは、「本当にこれがあのお仏壇なのか」と大変驚かれるとともに、心からお喜びいただきました。このたびは、節目となるお仏壇のお洗濯(おすすめコース)をお任せいただきまして、誠にありがとうございました。代々長くお付き合いをさせていただいているお手次寺様の大切なお仏壇ということで、いつも以上に気を引き締めて責任を持ってお仕事をさせていただきました。きれいに仕上がって喜んでいただくことができ、私どもも大変うれしく思っております。これからも末永くお参りいただければ幸いです。
今回は、約100年前に製作された彦根仏壇のお洗濯を紹介しました。彦根仏壇は、各工程を専門の職人が技術を尽くして仕上げる、まさに「技術の結集」といえる存在です。今回のお洗濯では、100年前の職人たちの卓越した技を間近に感じることができ、非常に貴重な機会となりました。今では入手が難しい贅沢な材料や、すでに失われつつある技法に実際に触れることで、改めて先人たちの技術の高さと、そのものづくりへの情熱を深く感じました。もちろん、新しいお仏壇に買い替えるという選択もあります。しかし、良いものを修理してきれいにし、次の100年へと受け継いでいけるのは、「大切に受け継いできたものを残したい」というお客様の想いと、職人たちの技術があるからこそです。私たちは、これからもお仏壇に込められたご家族の想いと、彦根で育まれた素晴らしい技術を未来へつなぐため、技を磨き続けて参ります。
※お仏壇の洗濯や洗浄については、詳しくはこちらをご参考ください >>「洗濯・洗浄」